_edited.jpg)
.png)
2024年<新連載>
『看護展望』× Nurse for Nurse コラボ企画
Nurse for Nurseではメヂカルフレンド社様の『看護展望』2023年載企画に続き、2024年も1年間の連載へ編集協力させていただきます。企画名は『看護のリーダーシップ「看護エキスパート」の経験から学ぶ』です。
毎号、様々な看護の現場(病院、在宅、看護教育機関、その他)でリーダーシップ を発揮しながら社会課題解決に向け挑戦している NfN の「看護エキスパート」(NfN 会員) に焦点をあてます。看護のリーダーシップとは何か、発揮するために⼼がけていること、 今後の展望など、これまでのキャリアの変遷を交えてご紹介いただきます。
本企画はNurse for Nurseコラボ企画にて、ご執筆者は記事掲載時点においてNurse for Nurseの会員(看護エキスパート)の方々です。
NfN会員であれば、ご執筆者との1対1のオンライン・キャリア相談が実現します。会員の方はご執筆者のプロフィール・ページから是非お申込みください。
連載記念イベント
看護のリーダーシップ『看護エキスパート』の経験から学ぶ
『看護展望』連載ご執筆者のキャリアや
リーダーシップについての発表をもとに、
一緒に「看護のリーダーシップ」を考えてみませんか?
.jpg)
<〆切:3月27日(木)正午>
視聴期間は3月28日まで
*NfN会員の方は会員サイトよりご覧ください。
ご登壇者の皆様からのメッセージ
.png)
本田和也さん
国立病院機構長崎医療センター
脳神経外科・教育センター
副看護師長/診療看護師(JNP)
私が看護師を目指し今後も続けて
いきたい理由とは?
看護師を目指す理由は、人それぞれ異なるものです。また、看護師としてどのような役割を果たし、誰に貢献したいのかという目標も多様です。私は看護師として18年間の経験を積んできました。その中で、5年間は看護師、10年間は診療看護師(NP)、3年間は看護管理者として働き、さらに4年間は医学・看護系および医療経営管理系の大学院で学んできました。このキャリアの軌跡を振り返り、「私がなぜ看護師を目指し、今後も続けていきたいと思っているのか、その理由とは?」という内容でお話しします。看護師を目指す方、看護師としてキャリアに悩んでいる方にとって、このイベントが何かのヒントになればと考えています。看護という仕事が、地域や臨床現場、そして私たち自身の人生にどのような輝きをもたらすのか、一緒に考えてみませんか?皆さんにオンラインでお会いできるのを楽しみにしています。ぜひご参加ください。

池亀俊美さん
公益財団法人榊原記念財団附属
榊原記念病院副院長兼主任看護部長
全身全霊で看護していたら、
Top Managerになっていた
「手に職をつけたい」という思いから、看護学校に入り、心臓に興味持ち、全身全霊で進んでいたら、Top Managerになっていました。「リーダーシップを発揮したい」という思いから、今も学び続けています。自分は何ものか、自分を知ること(自己理解)、自分は何を大切にしたいのか?人生100年時代を迎え、今自分は何に貢献できるのか、それを考え、実装するリーダーシップを模索しています。今回、多くのかたと、キャリア、リーダーシップについて対話できることを楽しみにしています。

山本則子さん
東京大学大学院医学系研究科
教授
看護の専門職性を高める
国家資格を持つ専門職として、私たち看護職は皆で看護の専門職性を高める努力を求められます。しかし、日本の看護学基礎教育・大学院教育では、そのような看護の専門職性を高める努力に関する教育をほとんど見たことがありません。米国での大学院教育で体験した看護の専門職性を高める努力に関する授業を参考にして、これから看護の大学院教育に必要なリーダーシップについて、みなさまと共に考えたいと思います。
1月号

本田和也さん
独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター
統括診療部 教育センター 副看護師長
同 脳神経外科 診療看護師(NP)
本田さんは「人にやさしく、自分には厳しく、誠実に看護を探求(向き合う)すること」という初心をもとにリーダーシップを発揮されてこられました。地域の課題解決のために診療看護師(NP) の資格を取得してからは、臨床での実践と共に診療看護師(NP) の活動推進に向けた検討にも携わり、現在は大学院で次世代の看護のリーダーシップをさらに発揮させるためのリスキリングを図っておられます。
3月号

山本則子さん
東京大学大学院医学系研究科 教授
公益社団法人日本看護協会 副会長
山本さんは「がんが治るものなら医学の力で治せばいいけれど、がんが治らない人のために何ができるのだろう」と考え、医師よりも看護師というキャリアを選択されました。そして、看護の現場での経験やアメリカでの学びを経て研究者になられ、当時の想いをもとに看護の実践を支える知の構築を目指してリーダーシップを発揮されております。リーダーシップを育むために役だった教育やネットワーク、山本さんが考えられる「看護のリーダーシップ」とは何かもご執筆いただきました。
5月号

木内昌子さん
一般社団法人MEPL 代表理事
一般社団法人日本医療的ケア看護職員支援協会 代表理事
木内さんは医療的ケアが必要な子どもたちの保育や教育を支えるための看護は治療のための看護や在宅生活を支える看護とも違い、新たな分野と捉えられています。そして、その人材育成と職能の確立を目指し「日本医療的ケア看護職員支援協会」を設立されました。医療的ケア児・者の「通いの場」で看護師が関わることで豊かな地域生活と共生社会の実現を目指し、リーダーシップを発揮しながらチャレンジを続けられております。
7月号

井倉一政さん
NPO法人三重ナースマネジメント協会理事長
トータルライフイノベーションCEO
井倉さんは保健所で保健師をされていた際に個人事業主として創業され、その後も様々な事業をけん引されています。NPO法人の活動ではメンバーと共に「看護の力でドキドキとワクワクを形に」しながら地域課題解決に取り組んでおられます。柔軟な発想と行動力で新しい社会資源を創造されてきたご経験、その中でリーダーシップを発揮する際に大事にされていることやその原動力についてご執筆いただきました。
9月号

山本典子さん
株式会社メディディア 医療デザイン研究所 代表取締役
山本さんは創業以来、看護師をされながら、看護師目線で医療現場の使いにくいものをデザインで問題解決されておられます。また、リーダーとして、原点を忘れず、毎日創意工夫を続けることが大切とお考えです。医療用サージカルテープカッター「きるる」の開発を機に、「だれを幸せにするか」というブレないデザイン思考で数々の賞を受賞されてこられました。この分野でリーダーシップを発揮されてこられたキャリアの軌跡をご執筆いただきました。
11月号

大川純代さん
国立研究開発法人国立国際医療研究センター
国際医療協力局 グローバルヘルス政策研究センター
上級研究員
大川さんは様々なライフイベントにある紆余曲折を乗り越え、現在は国際保健分野で研究者としてご活躍されています。そして、WHOガイドライン評価委員という国際的な基準や共通ルールをつくるために選ばれる専門家(規範セッター)の一人として、世界中の保健医療従事者や研究者をけん引されています。その大川さんがキャリアを歩む中で心掛けてきた3つのこととは。看護職でもありながら世界の保健医療を研究者としてリードされる今日までの歩みをご紹介いただきました。
2月号

池亀俊美さん
公益財団法人榊原記念財団附属榊原記念病院
(副院長兼主任看護部長)
公益社団法人東京都看護協会
(地区支部理事(多摩南))
池亀さんは「在りたい姿を思い浮かべ、優しさと強さ、思いやり、共感を大切にし、学びを繰り返し、対話を続けながらリーダーとしてどう在りたいか」を問い続けておられます。これまでのキャリアのなかでの挑戦、乗り越えられた課題、そこで味わった達成感についてご執筆いただきました。また、リーダーシップや組織開発の理解に役立ったリソースもご紹介いただきました。
4月号

大橋奈美さん
医療法人ハートフリーやすらぎ常務理事・統括管理責任者
日本訪問看護認定看護師協議会 代表理事
大橋さんは訪問看護認定看護師として現場でもご活躍されながら、医療法人の常務理事として経営にも携わられております。これまでの大橋さんのキャリアの変遷に加え、新卒訪問看護師の受け入れや職員にとって働きやすい職場づくり等、職員も利用者も幸せにする方法のヒントをご紹介いただきました。また、人材育成含め日々の業務のなかでは「既成の枠」を取り外し、「ゼロベース思考」を大切にリーダーシップを発揮されておられます。
6月号

水越真代さん
健康企業推進サポート シャイニングライフ
代表
水越さんは開業保健師として中小企業の産業保健・健康経営を支援しておられます。自らが先頭に立つのではなく、「健康づくりを通して、個人や企業が自社の在り方や自分の生活や生き方に気づき、自ら取り組むことができる支援をする力」を発揮しながら、日々業務にあたっておられます。自らは黒子に徹し、企業や従業員が主役となるよう「サーバントリーダーシップ」を用いてご活躍されています。
8月号

駒形朋子さん
東京女子医科大学 看護学部 看護管理学領域 准教授
駒形さんは数々の国際的なご経験から、多様化する社会において看護のリーダーには異文化の感受性と受容力や世界の看護に目を向けることが必要であると考えておられます。青年海外協力隊やGlobal Nursing Leadership Instituteへの参加、WHOの看護の報告書の和訳業務などを通して、その重要性を実感してこられたことについてご執筆いただきました。現在は看護師とロボットの協働のための調査研究を行いながら、学生の指導にも尽力されています。
10月号

福田裕子さん
まちのナースステーション八千代 統括所長
福田さんは千葉県で訪問看護ステーションや看護小規模多機能型居宅介護を運営されておられます。2023年には「千葉看多機連絡協議会」も設立され、様々な場でリーダーシップを発揮されておられますが、そこに至るまでには数々の失敗がありました。「事業所自体を実践も経営も広く見渡せるようになるには10年近くかかった」と言われる福田さんが大切にしていること、そして試行錯誤されながらリーダシップ・スキルを育まれてこられた様子をご執筆いただきました。
12月号

菅原由美さん
全国訪問ボランティアナースの会
キャンナス
代表
菅原さんはご家族を介護された経験から全国訪問ボランティアナースの会キャンナスを設立されました。その後も利用者のニーズに合わせて公的な制度では対応できないサービスを提供できるよう取り組まれてこられました。その中でリーダーとして大切にされていることは「自己決定」「自己責任」「自己判断」の3つです。会の設立当初は波乱に見舞われたこと、被災地支援含めたこれまでのご活動、今後の展望などをご執筆いただきました。
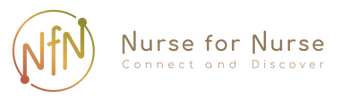.png)